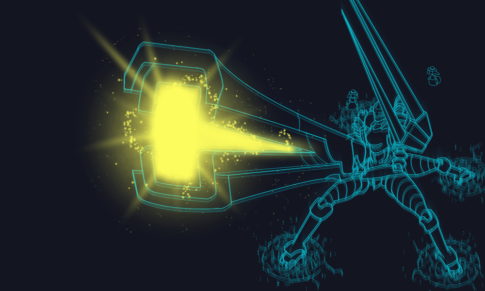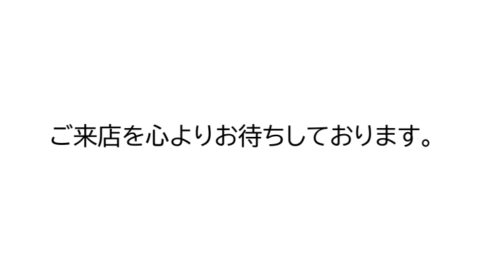3

二度目、あるいは三度目ともなる既視感。当初こそ違和感に悩まされていたものの、慣れてしまえば、むしろ好機であると捉えるようになった。
砂時計のことは不要に口に出さず、師匠のお気に入りである壺は厳重に扱い、虫除けの香炉もさも初体験であるかのように演じる。何もかもが順調で、気づけば初めて砂時計に触れた日――四度の虫除け香を焚く日を通り過ぎていた。
砂時計を使うと時間が巻き戻る。おとぎ話が現実になった今、少年の前には二つの選択肢があった。砂時計を頼るか、拒絶するか。当初の少年は後者を選んでいた。
しかし――。
「師匠っ、師匠!」
商人と貴族の行き交うこの町では珍しくない、馬車の事故。師事から六ヶ月目のある日、師匠は馬車に轢かれた。
子供を助けようとしたのか、それとも骨董でも庇ったのか。今となってははっきりしないが、少年が診療所に駆けつけた時にはもう遅かった。
「生きては、いるんです」
語る医者はひどく暗い目をしている。
事故から数日が経過しても、師匠は一向に目を覚まさなかった。呼吸はしているが意識を取り戻すことはなく、固く目を閉じている。
この状態になってしまうと医者もお手上げのようだ。彼らにできることは、奇跡が起こることを待つだけ。
「彼には世話になってるし、時が来るまで診てあげたいのは山々ですが……何せ、こんなご時世です。次から次へと怪我人はやって来るし、私のような町医者もいつ戦場に送られるか……」
配偶者も従業員もいない師匠には、少年しかいない。少年しか世話をできる人間がいない。どんな形であれ、彼には少年しかいなかった。
いつまでも診療所に留まっていると、どこからか「さっさと仕事をしろ」と怒声が飛んでくるような錯覚に陥る。
師匠に何があろうとも客は待ってくれない。骨董を求めて遠方からやって来る客や同業者もいる。彼らを蔑ろにするのは、それこそ師匠の意に反する。
少年は考える。考えて考えて、商売のいろはも知らぬ少年は、師の住処を守ることに決めた。
守るためには金が必要だった。
守るためには知識が必要だった。
守るためには時間が必要だった。
「……ごめんね、シェリィ。兄ちゃんは、立派なお店屋さんになるよ」
守るためには、砂時計が必要だった。