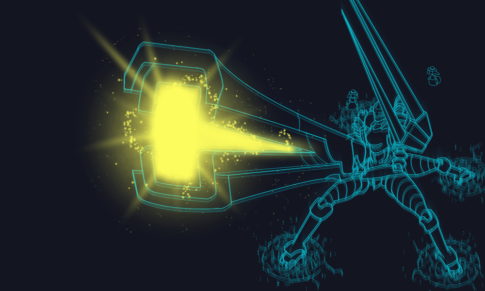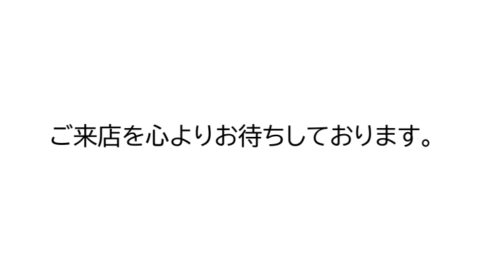5
「シェリィ、父さん、母さん!」
扉を開けると、家全体が揺れる錯覚に陥る。台所に面した居間と小部屋が二つ。慣れ親しんだ家は随分と古びて見えたが、ひとまず消失していなかったことに安堵した。弾む息をなだめながら、ゆっくりと辺りを見渡す。
「お、おにい、ちゃん?」
不意に聞こえてきたのは想像よりも芯の通った声だった。
顔を上げると、そこには女性が佇んでいた。どこか妹の面影がある、綺麗な女性だ。
「しぇ、り……?」
「お兄ちゃん、その……えっと、元気、だった?」
うろうろと妹の目が泳ぐ。ふわふわでそよ風にすら負けていたレモン色の髪はすっかり落ち着いて、丸めた絨毯のようだった体型はなだらかな曲線を描く。動揺に惑う手の一つ一つが大人びていた。いや、実際に『大人』なのだろう。
彼女の年齢は、見るからに少年を超えていた。
「あ、ああ。シェリィは……大きく、なったな」
「…………」
妹は何も言わなかった。ただ眉を下げて、じっと少年を見つめている。
「お兄ちゃん、疲れたでしょう。お茶、淹れるね」
ふと視線を逸らして、妹は台所に立つ。身長も輪郭も、記憶上の『妹』はまるで別物だ。妹には、どうしても――。
は、と息を飲む。頭を振って思考を落とす。
「お父さんとお母さんは」
ぴたりと妹の手が止まる。長い沈黙。コトコトとヤカンが揺れ始めた頃、ようやく妹は口を開いた。
「……お父さんは連れて行かれたよ。国のために戦えって。お母さんは――」
妹の目が部屋――かつて両親の部屋だった扉へと触れる。
「病気をして。それで……」
まさかと思った。父は徴兵、母は病死。妹はどれだけの間を一人で過ごしたのだろうか。震える手が鞄へと伸びる。
手紙では『元気だ』と記されていたのに。妹を、任せていられるはずだったのに。
「……ごめんね。お兄ちゃんに心配かけさせたくなくて。私、嘘、ついちゃった。でも――でもね、本当につい最近まで元気だったの。なのに突然、二人とも」
妹も混乱しているのだろう。たった一人で抱え込んできた真実を打ち明けたのだから。それも、自分より年下になってしまった『兄』に。
沈黙。ピンと張った空気は、とても実家のものとは思えない。あれから――少年が家を出てから、どれだけの時間が経ったのだろうか。恐ろしくて、想像する気にもなれない。
黙り込んでしまった少年を気にしてか、妹はぽつぽつと『空白の数年』を話してくれた。母のこと、父のこと、飼っていたニワトリのこと――婚約の話があったこと。とりとめのないことから聞き捨てならないことまで、妹は楽しそうに語ってくれる。
そう、楽しそうなのだ。楽しそう、なのだが、少年にはどうしても正反対の感情にしか見えなかった。
「……そろそろ日が暮れるね。ご飯にしよっか」
「料理できるの?」
「ふふ、お兄ちゃん、びっくりするよ」
悪戯気に笑う顔だけは昔のままだった。
■ ■
「お兄ちゃん、疲れたでしょう? 今日はゆっくり休んで」
食事を終えて案内されたのは、かつて両親のものだった部屋。隙間なくぴったりと並ぶベッドを見ると、かつての光景がよみがえる。
二人は日頃から愛の言葉をささやき合っていた。それも頻繁に。息子からすると目を背けたくなるような光景だったが、都会でたびたび見聞きした泥沼と比べると、かなり恵まれた家庭で育ったのだと悟った。
彼らはもういない。知らぬ間に、消えてしまった。
「ああ、日記……整理、しなきゃ」
巡りはじめた頭を沈めるべく、鞄から日記と筆記具を取り出す。両親の部屋には机がないから、ひとまずベッド横の戸棚を使うことにした。
空っぽの花瓶と古びた紙束を退けて、いつも通りに日記を開く。
「ひ……っ」
黒。黒黒黒黒。
少年待ち構えていたのは、紙面を埋め尽くす真っ黒いインクだった。幾重にも文字が刻まれて、まるでインクをこぼしたかのような有様になっているらしい。
くり返した日々も、消えたはずの罪も。決して少年を逃しはしなかった。
「あ、ぐ、う……っ」
叫び出しそうになるのを殺して、少年は呻く。
くり返した日々はとにかく必死だった。どこを間違えて、いかに修正しようとしたか。全てを記録して記憶して整理して、やっとのことで『最適の道』を導き出した。日記がなければ、少年の小さな頭はとうの昔に限界を迎えていたはずだ。逆に言えば、日記があったからこそ少年の商売は上手くいったのだろう。
この日記は第二の共犯者だ。同時に観測者でもあった。
「なくなったわけじゃ、なかった……」
ベッドに身体を放る。ゴツゴツとした枠が背骨を抉る。その痛みすら、少年の顔を動かすことはなかった。