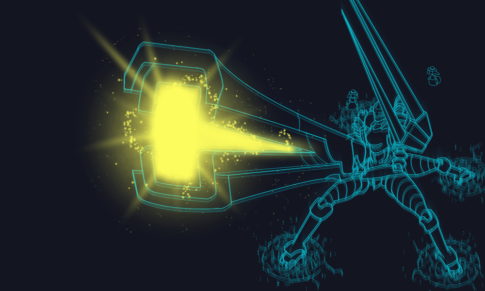この作品は、小説家の三浦常春さん @tsune_yeah に依頼し、執筆いただいたものです。
三浦さんのpixiv上でもこの作品を読むことができます。
【pixiv】精霊の砂時計【SKIMA納品】 https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=19220971
【SKIMA】 https://skima.jp/profile?id=277418
【カクヨム】https://kakuyomu.jp/users/miura-tsune
1
砂交じりの風が吹きつける。コトコトと揺れる窓を一瞥して、少年は火を持った。足元には小さな香炉。灰に鎮座する香に火を点けると、すぐに細い白煙が立ち上った。
ここは〈ノウィロの町〉。農業に適さない土壌ながらも川と地形に恵まれ、今や商業の中心地として名を馳せている――らしい。
らしい、というのも、少年はこの町の生まれではなかった。「〈ノウィロの町〉に行けば仕事にありつける」、出所も真偽も定かではない噂を聞きつけて上京したに過ぎない。彼の出自は、この町から少し離れた場所にある田舎にある。
「ふう、これでよしっ」
香炉から顔を上げて、少年はようやく一息つく。ツタ植物のあしらわれた香炉からは、ツンとした香りが漂う。爽やかながらも鼻の粘膜を刺すような鋭い匂いだ。
一ヶ月に一度、この倉庫では虫除けの香を焚く。この単純に見えて大切な作業は、骨董商の弟子たる少年の仕事であった。これでもう四度目になるだろうか。
「流石に慣れたかな。まあ単純な作業だし、間違えようもないんだけど」
こつり、と踵に何かが当たる。足の置き場に気をつけつつ、そうっと移動する。
陽が差さない北側に位置するこの部屋は日中でも薄暗い。古風な机に細やかな装飾の施された鏡。刺繍の細かい布地に宝石を散りばめた贅沢な衣装。古今東西の価値ある品が詰め込まれた部屋も、光がなければただの物置でしかない。
いくら日光が天敵といえど、やりすぎではないだろうか。当初の少年はそう思ったものだが、師匠曰く、これでも――夜と朝の境目ほどの暗さでも不十分なのだという。
つまずいてしまわないよう気を配りながら、少年は香炉が入っていた小箱を片付け始める。
視線を感じてふと顔を上げると、そこには鏡台があった。隠し布のずれた、大きな鏡台。奥まったところにあることから、随分と長い間をこの倉庫で過ごしているらしい。
このままでは埃まみれになってしまう。布をかけ直してやろうと近づくと、ふと台の上に小さな置物を見つけた。
「ん、なんだこれ。砂時計?」
砂時計は工芸品として珍しくない。多分、ガラスの加工に理解のある地域ではそれなりに作られていることだろう。
「こんな小さいもの、剥き出して置いておいたら失くしちゃうだろ……案外抜けてるところがあるんだな、師匠も」
窓の隙間から差し込む細い光に照らしてみると、夜明けの空のような砂がさらりと動いた。周りを包むガラスは見失うほどに澄んでいて、きっと海底とはこのような感じなのだろうと夢想する。
――ああ、綺麗だな。
導かれるように、少年はくるりと時計を返した。
■ ■
「新入り。これからお前に重要な仕事を授けよう」
そう切り出した師匠はどことなく浮かれた様子だった。いつもよりも声が弾んでいる。弾んではいるのだが、少年は得も言われぬ違和感を覚えていた。
「虫除けならさっき焚いた――」
「なーに言ってんだ、お前は。そら、つべこべ言わずに行くぞ」
ぶっきらぼうに言って、師匠は倉庫の方へと向かっていく。骨董商にしては屈強な身体を持つ師匠は曲がったことが嫌いだ。揶揄や冗談も例外ではなく、たとえ客相手でもそういった言葉を口にすることはない。ないはず、なのだが。
「虫除けの時はこの香を使うんだ、ツンとした匂いのやつだ。隣のいい匂いのヤツと間違えるなよ」
「師匠、その話は前に聞きました。ついさっきだって焚いたし、もう何回か任せてもらってる。その……いろいろ教えてもらえるのはありがたいけど」
香炉を出して香を入れて火をつける。たったそれだけの作業を何度も聞き直さなければならないほど、少年の記憶力は衰えていない。
とはいえ、師匠は師匠で痴呆を患ったわけでもないだろう。復習を兼ねて大人しく話を聞いていると、彼は少年を倉庫に招いて香炉の仕度を始める。その隙に影の奥――しかと布をまとった鏡台に目をやる。そこには凛と、あるいはこっそりと、砂時計が座っている。
「――師匠」
「なんだ」
「あそこにある砂時計……あれって何なんですか?」
少年の問い掛けに、師匠は怪訝な表情を浮かべる。だがそれも一瞬のことで、彼は香炉に灰を入れ始めた。
「ただの砂時計だよ」
「ただの砂時計を骨董屋の倉庫に眠らせているんですか?」
そこまで食い下がって、ようやく師匠は顔を上げた。灰にまみれた匙を置いて、身体を前に倒して、まるで物語りでもするかのようにこっそりと告げる。
「あれはいわくつきのものでな。ひっくり返すと魂を抜かれちまう。おかしくなっちまうんだ」
「え……」
魂を抜かれる。思わず心臓を押さえる。その仕草を師匠は見逃さなかった。ぐっと眉間に皺を寄せる。
「まさか、ひっくり返したのか」
少年は何も答えられなかった。倉庫に眠るガラクタの数々は、師匠にとっては商売の道具にほかならない。よほどのことがない限り、弟子たる少年が触れることは許されないはずだった。
師事当初の約束事を破ってしまった。露呈してしまった。大事な大事な契約を。
「ごっ、ごめんなさい! で、でも、本当に、ただの砂時計だと思って……」
口を開こうとした師匠を遮って、少年は頭を下げる。少年の反省をしかと受け取ったのか、師匠はぐっと巨躯を伸ばした。
「……まあ、一見するとただのキレイな砂時計だしな。それに、『魅入ってしまう』って意味の『魂を抜かれる』かもしれねぇ。あまり気に病むな」
「師匠……」
「だが、約束を守ったのはいただけねぇなァ。昼食を摂ったら契約書の書き取りでもしとけ」
「い、嫌だ! それだけは嫌だ!」
「約束を破ったのはどこのどいつだ? それに、約束を破ったのは今回が初めてじゃないよな。夜に町を出歩いたろ。俺に隠れて夜食も食ってたな? そもそも、倉庫には無断で入るなって言いつけてあったろ」
「なんで知って――あ」
「破門にならないだけありがたく思え」
そこまで言われると、少年は何も返すことができなかった。
■ ■
一度は晴れたはずの疑惑が浮上したのは夜のこと。修行に出てから日課となった日記帳を開いた時のことであった。
ランタンに火を入れて、ガタつく椅子に腰をかける。机の上に置いたままの日記帳は、実家を出る時に家族から贈られたものだ。骨董屋に師事してから約四ヶ月。足腰の痛みに呻く日もしこたま怒られて滅入った日も、欠かさず何かを記してきた。
日記はよいものだ。今日一日の出来事を整理できるし、文字の勉強にもなるし、何よりも妹に宛てた手紙の話題に困らない。日記を見返せば、『面白い話』はたくさん埋まっているのだから。
今日は何を残そうか。記憶を探りながら本をめくる。筆の先にインクをつけて、呼吸を整える。そこでようやく違和感に気づいた。
日付が違う。
前後の紙をめくってみても、日記の方に落ち度はない。それなのに記したはずの記録が、刻んだはずの失敗が、文字通り白紙になっていた。
「な、なん、で……」
めくってめくって、ようやく気づく。師事してから、まだ一ヶ月しか経っていない。それなのに、少年の記憶には『四回目の虫除けの香』を焚いた記憶がある。
確かに見た。その光景を見た、はずなのだ。
「戻って、る……?」
少年の脳が辿り着いたのは、お世辞にも現実的とは言えない空想であった。
まさかと失笑する少年であったが、この現象は『そう』としか説明できなかった。あるいは少年がおかしくなったか。
「疲れてるんだ、契約書の書き取りなんてさせられるから」
記録もそこそこに少年はベッドへと横たわる。布団越しでも感じる床板はいつも通り硬かった。
「あっ、シェリィへの手紙、そろそろ出さないと」