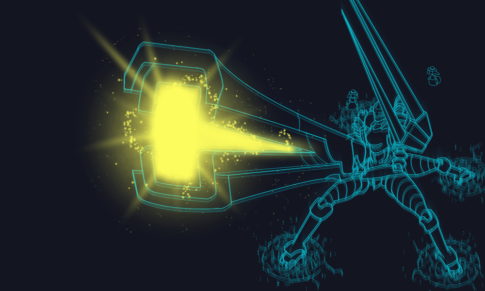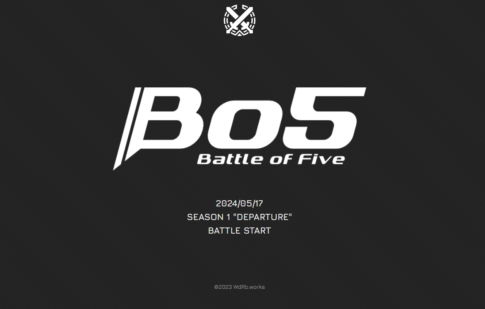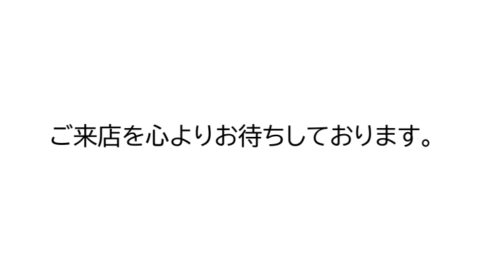6
少年の足には文字が絡みついていた。日が沈んで、朝が来て、気を失うように眠って。それを何度くり返しただろうか。底の抜けた靴で辿り着いたのは、緑豊かな都市だった。
〈ノウィロの町〉ほどごった返してはいないが、道行く人々の身なりはおとぎの国のように整っている。ひょっとしたら、これこそが俗に言う『楽園』なのかもしれない。
いよいよおかしくなったか。フ、と口の端から息がこぼれる。
「おい、そこの。そんな格好で町に入るつもりか? 悪いことは言わん、よせ。裸で入る方がマシだぞ」
嘲笑を飛ばしてきたのは白銀の甲冑だ。高くそびえる城門に寄りかかっている。よく手入れされた甲冑に武器。志高くこの門を守り抜いているのだろう。くり返しもせず。
「もし、旦那様。御慈悲をくださいませんか」
「物乞いなら他所へ行け、鬱陶しい」
「わたくしは商人。砂に流されてここまでやってきました。一つ、紹介したいものがございます」
愛用の日記も筆記具も、妹への手紙も、金目のものは全て置いてきた。少年の手には小さな砂時計があるのみ。
「これは『精霊の砂時計』。旦那様の願いを叶えてくれる不思議な時計です。旦那様の気が済むまで、好きな時間をくり返すことができます」
「これが?」
あと一度だけ――そう思って、何度砂時計をひっくり返しただろうか。これのおかげで今の少年があることは紛れもない事実だが、一方で、歩むはずだった人生から逸れてしまった。
本当は、自分だけの店を持って、家族を楽にしてやりたかっただけなのに。
「そんな神器を持っているにも関わらず、なぜお前はそんな身なりなんだ」
「必死に歩いてきたからです。貴方様に会いたくて」
衛兵は考える。
少し待て。そう声をかけて、衛兵は部下に金を持ってこさせる。皮袋は拳一つ分ほどに膨らんでいる。これだけあれば、商売を始めるまでの資金にはなるだろう。
そこまで考え至って失笑する。何はともあれ、これで最後だ。これで都合のよい人生は終わる。
「ほら、これで充分だろう」
金を受け取って、砂時計を渡す。
渡す寸前、ふと思う。
首を、ひねる。
「おい、早く渡せ」
砂時計が笑った気がした。
「やっぱ『なし』で!」
―了―