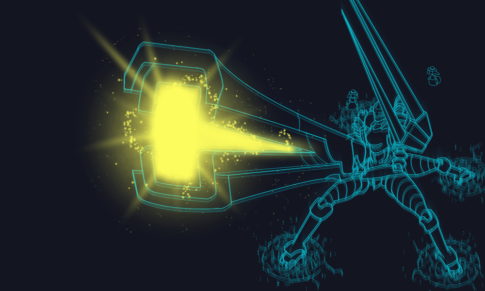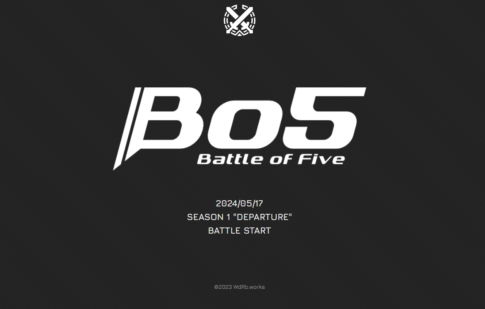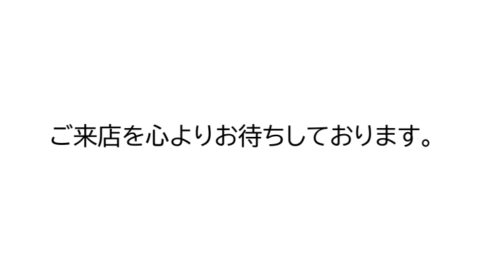2

「やあ、おやじさん。いい壺は入っているかね。花を生けたいんだ、娘がキレイなのを摘んできてね」
「ああ、どうも。それなら西国で生まれたガラス製のものはどうです。まだ『骨董』と呼べるほど年を取ってはいませんが、いい品ですよ」
「ということは、我が家で『骨董』が生まれるかもしれないのか。うん、面白い!」
見覚えのある客。聞き覚えのあるやり取り。書き覚えのある数字。日常における一場面から仕事上の些事に至るまで、全てが『二度目』であるかのように感じる。
夢で見たことがある、なんてことは度々あったが、これはその類ではない。それよりもずっとはっきりとしていて、ともすれば確信めいたものすら少年の内に宿っていた。
頭がおかしくなりそうだ。ありえないはずなのに、心が、記憶が、否定している。次第に仕事に身が入らなくなり、とうとう師匠にも咎められてしまった。
「商売は身体が資本。ろくに休ませることもできないなら、一度実家に戻るか?」
「……いえ、まだ。まだもう少し……やらせてください」
「それならしゃんとしろ。骨董商として生きるなら、名もなき砂時計ごときに負けてらんねぇぞ」
古今東西の品を収集し、次の持ち主へと繋ぐ仕事――骨董商。人々の生活を支える品からいわくつきの品まで、ありとあらゆる『物』を扱う。あの砂時計は、その中のたった一つに過ぎない。
分かっている。分かってはいるのだ。
とにもかくにも、今の少年にできるのは、砂時計に触れないことだけだった。もう二度と使うまい。そう心に決めていたはずなのに。
「やってしまった……」
少年の足元には壺。正確には、壺だったもの。宝石に金の糸細工。透き通るような磁器の破片。それが無残にも石の床に散らばっている。
仕事の代わりに屋敷中の清掃を言いつけられていた時のことだった。
この壺は屋敷の主人たる師匠の私物で、たびたび眺めるくらいにはお気に入りの品だ。一度だけ値段を訊いてみたことがあった。当時ははぐらかされてしまったが、少年の乏しい知識を総動員しても高価なものであると推測できる。
初犯ならば許されたかもしれない。しかし少年の『不注意』はこれが初めてではなかった。ある時は放り投げた雑巾を当て、ある時は怒り心頭の師匠から逃げている時につまずいて、またある時は、遊ぶ金欲しさに小物を売り払ったこともある。
小物の件は幸いにも露呈していないが、それでも契約書の書き取り以上の罰は避けられないだろう。
血の気が引いていく。少年は出稼ぎの身だ。家族に生活費を送るために上京してきた。それなのに破門されようものなら、どんな顔で両親に、妹に会えばよいか。
気づけば、少年の足は倉庫へと向かっていた。
■ ■
「お兄ちゃん、絶対に帰ってきてね。立派なお店屋さんになんか、ならなくていいから」
出立の日。大好きな妹としばしの別れ。大きな瞳に涙を湛えて、それでもこぼさないように上を向いて。健気に見送る妹の姿はよく覚えている。
まさかもう一度見られるだなんて、夢にも思わなかった。